退職代行サービスって聞いたことはあるけど、実際サービスを受けることになると、どれくらいの費用がかかるんだろう?退職代行サービスで、一番費用を抑えることができるのはどれだろう?
実際に、退職代行サービスの利用を考えているけど、費用がいくらかかるのか、気になる方もたくさんいらっしゃると思います。料金を聞いて、サービスを利用するかどうかを検討する人も多いでしょう。
退職代行サービスを利用する際は、費用に見合うサービス内容があるかを確認し、最も自分に適した業者を選ぶことが大切です。退職代行サービスの平均的な費用の相場は、現在3万円〜5万円程度となっています。
料金が安いという理由だけでサービス会社を選んでしまうと、結局退職する企業と直接やり取りをすることになり、トラブルに発展してしまう可能性もあるのです。そんな事になれば、退職代行を頼んだ意味がありませんよね。
コストだけで業者を選ぶのは非常にリスクが高く、おすすめできません。
本記事では、退職代行サービスの価格相場や費用、各サービスの違いについて解説していきます。現在退職代行サービスを利用することを検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。
退職代行とは?

「退職代行サービス」とは、労働者本人の代理として、弁護士や代理人から、労働者が勤める会社に退職の意思を伝えるサービスのことを言います。
会社に退職の意思を伝えたところ、上司から執拗に引き止められた、今辞めるなら損害賠償を請求すると脅された、嫌がらせを受けた、そういった話を聞いたことがある方も少なくはないでしょう。
退職代行サービスでは、「会社が辞めさせてくれない」といった悩みを持つ労働者に代わって、退職願を提出してくれるのです。
10年以上前から続く退職代行サービス
近年では、さまざまなメディアで退職代行サービスが目につくようになり、その浸透率も高まってきています。
以前はあまり周知されておらず、比較的新しいサービスのように思われがちですが、実は10年以上前から「弁護士の業務の一部」として存在していたのです。
ただ、現在のようなサービスではなく、未払い残業代の請求など『相談の過程で発覚した労働問題』や、労働条件の悪い会社に勤めており、退職することが難しい労働者に代わって、弁護士が退職手続きを行うのが一般的なサービスでした。
退職代行の成功率
全ての企業は、民法627条に基づき退職を申し出てから2週間で退職できると定められています。
退職代行サービスのHPなどを見ると、「退職成功率は100%です!」と宣伝しているものはよく見受けられますが、これは法律に基づいて2週間で退職した場合も含まれています。
これが迅速かつ円満な退職と言えるでしょうか?企業によっては、一定の時間や労力を必要とする場合もあるので、たとえ退職の成功率が100%と書かれていても、必ずしも迅速かつ円満な退職が保証されているわけではないのです。
退職代行の流れ
では、実際に退職代行サービスを利用する場合の流れを見ていきましょう。退職代行は、主に以下の6つの段階ごとに進みます。 ひとつひとつ、詳しく説明します。
- 申込みまたは相談
- 労働者の情報を伝える
- 料金の支払い
- 今後の流れを担当者と打合せ
- 担当者が実行し、その経過報告をする
- 担当者から利用者にヒアリング
①申込みまたは相談
まず、利用者が退職代行サービスへの申し込みを行います。業者から勧誘することはありません。必ず労働者本人が申し込みをすることになります。
業者への連絡方法は、一般的には電話やメール、LINEを使用することが多いです。
基本的に相談料が発生する退職代行専門サービスはありません(法律事務所を除く)。有給休暇や退職金の扱い、不払いリスクなどの不安な点がある時は、無料相談をしてから申し込むことをおすすめします。
②労働者の情報を伝える
申し込みが完了すると、次に利用者(労働者)の情報を業者に共有します。
- 必要な利用者の個人情報:氏名、生年月日、住所、連絡先、雇用形態、勤続年数、契約期間、身分証明書(画像付き)、希望の退職時期など
- 所属している会社の情報:会社名、勤務先の電話番号、所属部署など
「有給休暇をすべて消化したい」「私物を返却してほしい(もしくは処分してほしい)」「離職票等の必要書類の送付を希望」など、退職時の希望がある場合は、この段階で伝えておきましょう。
③料金の支払い
必要になる情報を全て共有したら、今後の流れやサービスの価格についての説明を受けます。退職代行サービスはほとんどの業者が前払いですので、打合せに入る前に料金の支払いをする必要があります。
支払い方法は業者によってバラつきがありますが、現金振り込みやクレジットカード払いが一般的です。その他にも、LINE Payやビットコインなどの電子マネーでの支払いに対応している場合もあるので、業者に確認してみると良いでしょう。
業者が利用者の支払いを確認したら、ここから退職手続きが始まることになります。
④今後の流れを担当者と打合せ
具体的な面談では、ヒアリングシートを使用し、すでに共有している情報以外にも、さらに詳細な部分まで質問を受けます。この面談を行うことで、具体的な内容を決めていきます。
スムーズに進めていくためには、自分の希望をできるだけ詳しく伝えることが重要です。
- 勤務先に退職を伝える日程
- 退職の理由
- 退職を希望する日
- 会社からの貸与品の有無
- 発行を求める書類
- 返却や処分を求める私物の有無
- 有給休暇や退職金について
代行業者には、スタッフ1人1人の役割を利用者が指定し、利用者からスタッフに指示することもできます。しかしこのやり方だと、自分の退職理由や希望を他人に代弁してもらっているのと同じです。
代行業者に頼むのなら、希望日時と勤務先に伝えたい内容を決めて、後はプロのやり方に任せたほうが安心だと言えるでしょう。
⑤担当者が実行し、その経過報告をする
次に、ヒアリングシートを使った面談をもとに、担当者が勤務先に退職の希望を伝えます。
一度のやり取りで退職が成立する場合もありますが、何度か連絡する必要がある場合もあります。いずれの場合も、利用者は途中経過の報告を受けるだけで、勤務先の相手と直接やりとりする必要はありません。
利用者の退職の意思を受け、利用者と勤務先の双方が必要書類を確認したら、これで退職手続きは完了です。
⑥担当者から利用者にヒアリング
利用者が退職した後も、フォローアップを行っている代行業者もいます。例えば、利用者が転職のサポートを希望した場合、退職代行業務が完了した後でも相談することが可能であったり、失業手当の申請を行ってくれたりするのです。
アフターフォローの有無は、業者によって異なります。このようなサポートを希望する場合は、業者に確認してみると良いでしょう。
運営元の違いによる退職代行の料金相場

次に、退職代行サービスを提供している3社のサービス料金の違いを見ていきましょう。
| 運営元 | 料金相場 | 会社と交渉 |
| 労働組合 | 25,000~30,000円 | 〇 |
| 弁護士 | 50,000~100,000円 | 〇 |
| 民間企業 | 10,000~50,000円 | × |
労働組合: 25,000~30,000円
労働組合が運営する退職代行サービスは、相場は25,000~30,000円程度です。労働組合の場合、労働組合法によって団体交渉権や団結権が保障されています。
従って、会社と交渉することが可能であり、法律に基づいて退職手続きが行われるので、違法性がなく安心です。
弁護士:50,000~100,000円
退職代行サービスを弁護士事務所に申し込むと、50,000円~100,000円程度の費用がかかります。
弁護士に頼むと高額になるイメージを持っている人も多いですよね。しかし、弁護士が提供している退職代行サービスは、退職がスムーズにいかない時など、困った時に強い味方となってくれるという理由から、支持されています。
民間企業:10,000円~50,000円
民間企業が提供する退職代行サービスの相場は、10,000円~50,000円程度です。
もちろん、低価格で充実したサービスを提供する業者もあるのですが、支払い後に連絡が取れなくなるなどのトラブルの事例があるのも事実です。
民間企業が提供するサービスを利用する際は、口コミなどをよく確認してからの方が良いでしょう。
業者ごとに異なるサービス内容

退職代行業者は、一般企業、弁護士、労働組合法人の3種類に分けられ、それぞれ提供しているサービスの種類や内容に違いがあります。
以下、それぞれの事業者の特徴について見ていきましょう。また、メリット・デメリットについてもご紹介します。
労働組合運営は安価だが会社と交渉可能
労働組合法人が運営する退職代行サービスは、相場が25,000円から30,000円程度と安価であり、パートタイム労働者も利用できます。さらに、民間企業とは違い様々な交渉ができるメリットもあります。
- 有給申請や有給の買取交渉。
- 未払い賃金の支払い交渉。
- 退職金の交渉
- 「辞めさせない」などの企業とのトラブル対応
- 離職票などの書類発行依頼
上記のような交渉を行うことで、会社の言いなりになることなく、労働者としての権利を行使することができます。裁判になった場合対応は難しくなりますが、退職を申し出て会社から裁判を起こされることはまずないでしょう。
費用を抑えながら安心して退職代行サービスを利用したい方は、労働組合法人が運営する退職代行サービスがおすすめです。
弁護士運営はあらゆるパターンにも対応できる
弁護士が運営する退職代行サービスでは、交渉だけでなく裁判にも幅広く対応できるというメリットがあります。
利用者は次の内容に該当する場合、退職時に会社から損害賠償を請求される可能性があるので、覚えておくと良いでしょう。
- 引継ぎを拒否し取引先を失った
- 引継拒否が就労規則違反
- 会社の機密情報を漏らした
- 有期契約期間内の不当な退職
- 同僚の引き抜き
- 経費による留学や研修直後
弁護士が運営する退職代行サービスには、依頼者の代理人として裁判を行えるというメリットがあります。しかし、裁判にかかる費用は10万円以上になることもあり、費用の面ではかなり負担を背負うことになるでしょう。
もし企業とトラブルを抱えている場合には、弁護士の提供しているサービスを利用しましょう。しかし、特段トラブルがない場合は、他の企業でも問題なく退職できます。
一般企業は会社交渉が難しい
民間企業が運営する退職代行業者が、企業と様々な交渉をするのは弁護士法違反となり、給与や未払い金などについて交渉はできないことになっています。民間企業として退職代行できる業務は、『退職の意思を会社に伝えること』だけです。
会話中に交渉が行われることもありますが、これは違法となってしまいます。会社側が違法と知れば、退職は難しくなりトラブルに発展するかもしれません。
しかし費用が安価なため、アルバイトやパートタイマーでも気軽に依頼できると、最近では問い合わせが増えてきています。
各退職代行業者の料金と特徴をご紹介

退職代行サービスの言葉を、最近インターネットで良く目にするようになってきました。
昔は弁護士に依頼するのが当たり前でしたが、現在は弁護士というだけでハードルが高く感じたり、予想以上に費用がかかったりするので、他の企業が人気になってきています。
そこで今回は、おすすめの退職代行サービス9社をご紹介していきましょう。
それぞれの企業の料金や対応の早さについてもまとめていきますので、サービスの利用を考えている方は参考にしてみてくださいね。
おすすめの退職代行サービス一覧
- 退職代行オイトマ
- SARABA(サラバ)
- ニコイチ
- 辞めるんです
- EXIT(エグジット)
- 退職代行Jobs(ジョブズ)
- クラウドエンマン
- 退職代行ガーディアン
- Re:start(リスタート)
退職代行OITOMAの料金と特徴
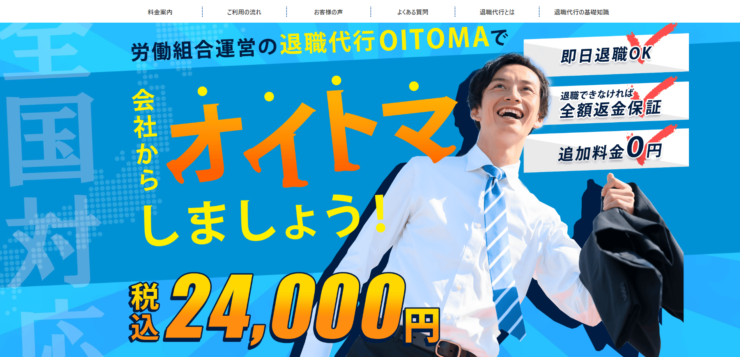
出典:退職代行オイトマ公式
退職代行「オイトマ」の人気のポイントは下記になります。
- 業界最安値の24,000円でサービスが利用可能
- 24時間いつでも対応可能
- 退職できなかったら全額返金保証
OITOMAは退職代行サービスの中では業界最安値となっており、その中でも、依頼したその日のうちに退職できる、「即日退職」が人気の退職代行サービスです。
24時間365日対応なので、平日・休日関係なく退職の依頼ができます。さらに、OITOMAでは退職後の転職支援や退職後のフォローアップも行っています。
OITOMAは、とにかくすぐに退職したい方におすすめの退職代行サービスです
| 料金 | 24,000円 |
| パート・アルバイト料金 | ◎ |
| 返金保証 | 全額返金保証 |
| 弁護士監修 | – |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日対応 |
退職代行SARABAの料金と特徴
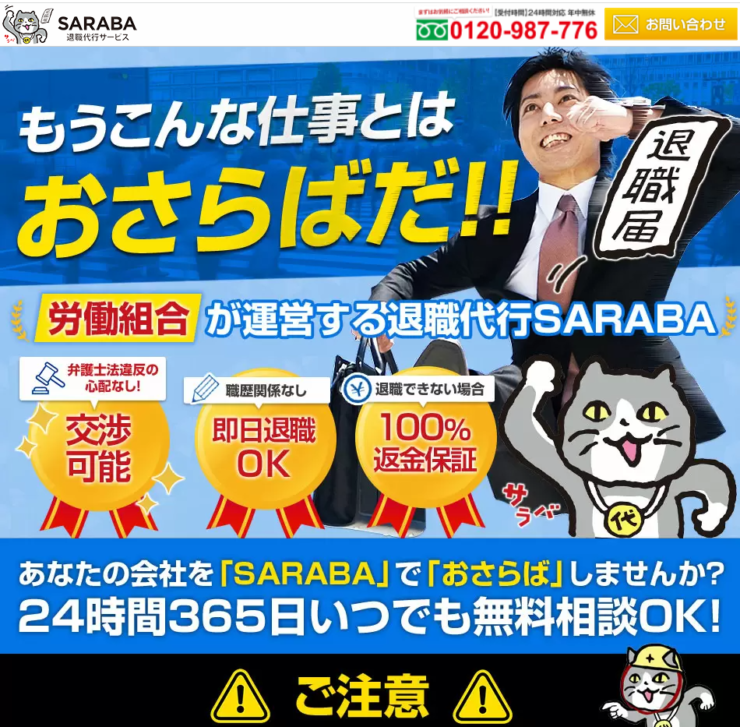
出典:退職代行SARABA
SARABAのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 労働組合が運営しておいりので安心
- 企業と交渉可能
- 退職できなければ全額返金保証付き
SARABAは労働組合が運営している退職代行サービスです。労働組合は弁護士同様、退職金などの調整・交渉を行うことができます。そして、もし退職ができなかった場合は全額返金保証があるのも嬉しいポイントですよね。
料金は職業に関係なく一律であり、追加料金は一切かかりません。相談は24時間365日無料で、即日対応してくれます。
トラブルなく企業と交渉を行い、安心して退職したい方におすすめの退職代行サービスです。
| 会社名 | 株式会社スムリエ |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | 25,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | 25,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
退職代行ニコイチの料金と特徴

出典:退職代行ニコイチ
ニコイチのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 退職代行実績は16年!
- 退職した人の累計実績は29,000人以上
- 退職できなければ全額返金保証付き
ニコイチは退職代行サービスを行って16年の実績があり、業界では老舗の部類に入る会社です。
累計29,000人以上の退職をサポートしており、業界トップクラスの実績を誇っています。
弁護士が監修しているにもかかわらず、料金も手頃な点が人気のポイントですね。万が一退職できなかった場合は、全額返金保証もあります。
退職後は、転職エージェントを無料で紹介してくれるなど、アフターフォローも充実しているので、実績と料金で退職代行サービスを決めたいなら、ニコイチがおすすめです。
| 会社名 | 株式会社ニコイチ |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | 27,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | 27,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
辞めるんですの料金と特徴

「辞めるんです」のおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 業界初の後払いが可能
- 浅い年数でも確かな実績
- 追加料金なしでリーズナブル
「辞めるんです」は2019年に設立された企業ですが、今まで7000人以上を退職させてきた実績をもっています。
辞めるんですが人気の1番の理由は、料金の後払いが可能な点です。
退職代行サービスを依頼したからといっても、スムーズに退職できるか不安ですよね。
しかし「辞めるんです」では、退職がきちんと認められるまで費用が発生しないので、安心してご利用いただけます。
さらに、退職堕一行業務は弁護士が監修しているにもかかわらず追加料金は発生せず、リーズナブルな料金設定になっているのも魅力的ですよね。
退職代行サービスの品質に不安がある方は、後払いサービスを提供している「辞めるんです」がおすすめです。
| 会社名 | LENIS Entertainment株式会社 |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | 27,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | 27,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
退職代行EXITの料金と特徴
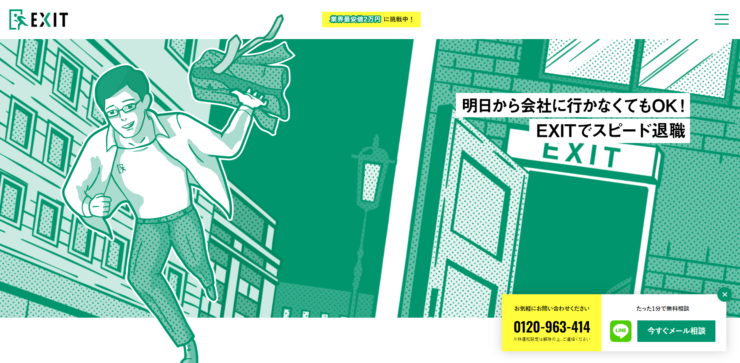
出典:退職代行EXIT
EXITのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 何度でも相談無料、即日対応
- 転職サポートが充実!
- 2度目の利用は10,000円off
EXITは、何度でも無料相談ができ即日対応も可能です。
休日や深夜でも相談が可能なので、平日はなかなか時間が取れない方や、遅い時間まで働いてる方でも利用しやすくなっています。
EXITの1番の魅力は、転職サポートが充実していることです。
サービスの1つとして、EXITは転職エージェントと提携しています。そのサービスを利用して転職が決まった場合、退職代行費用を全額キャッシュバックしてもらえるのです。
また、2回目の退職代行サービス利用時には1万円の割引があるので、もし次退職希望があった際には安価でサービスを利用できます。
| 会社名 | EXIT株式会社 |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | 50,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | 30,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
退職代行Jobsの料金と特徴

出典:退職代行Jobs
退職代行Jobsのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 顧問弁護士の情報がすぐに分かる
- 労働組合に加入できる
- 追加料金・期間制限はなし!
退職JOBの強みは、顧問弁護士を前面に出して紹介していることです。
他社は『弁護士が監修して…』とありますが、弁護士名を明記しておらず、どのような人が監修しているのかわかりません。『退職JOB』は顧問弁護士である西前恵子先生の動画コメントまであり、信憑性は非常に高いと言えます。
また、顧問弁護士だけでなく労働組合とも連携しており、依頼時に直接組合に加入することも可能です。
すぐに退職できなくても、退職手続きが完了するまで、無期限でフォローしてくれるのも安心感がありますよね。
| 会社名 | 株式会社アレス |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | 27,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | 27,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
クラウドエンマンの料金と特徴
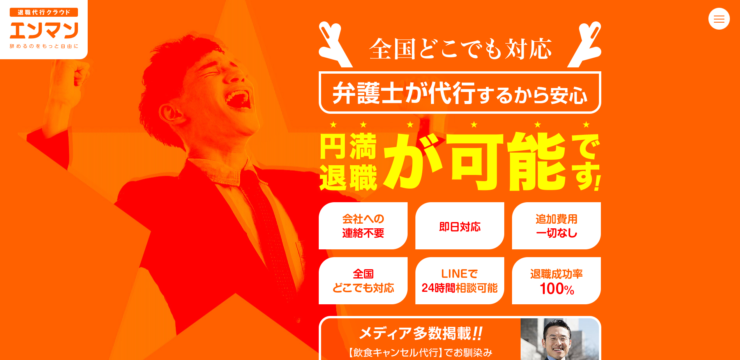
出典:退職代行クラウドエンマン
クラウドエンマンのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 弁護士を代理人とすることが可能
- 退職後2ヶ月間、書類作成などのフォローアップが可能
- プレミアムプランでは、より手厚いサポートを提供
「クラウドエンマン」は他社では珍しく、弁護士が代行業務を請け負ってくれます。他社に比べると料金は高めですが、弁護士が直接関わってくれるのはとても心強いですよね。
退社後も、必要書類の相談など2ヶ月間無料でフォローしてくれます。プランにはスタンダードとプレミアムがあり、プレミアムは給与や退職金の交渉が可能です。
突然の退職を有利に終わらせたいなら、クラウド・エンマンがおすすめです。
| 会社名 | 法律事務所アルシエン |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | スタンダード:33,000円
プレミアム:55,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | スタンダード:33,000円
プレミアム:55,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
退職代行ガーディアンの料金と特徴
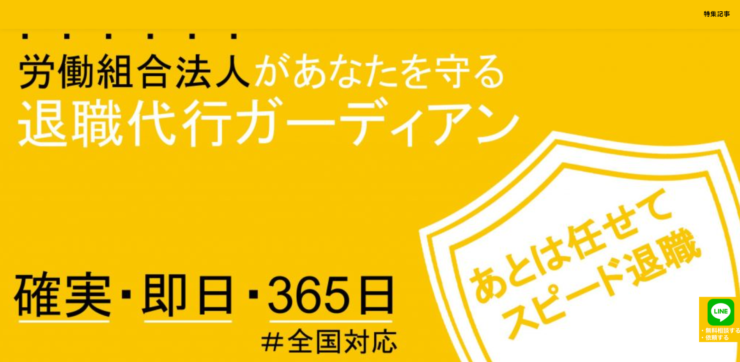
出典:退職代行ガーディアン
退職代行ガーディアンのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 労働組合が運営しており安心
- 賃金に対する交渉も可能!
- スマホだけで退職までが完了
先に紹介した「退職代行オイトマ」と同様に、「退職代行ガーディアン」も、労働組合が運営しています。
労働組合が運営しているので、賃金や労働時間に関する交渉を弁護士を介さずに労働組合が直接交渉可能です。
弁護士に依頼するよりも安価ですが、交渉も可能ということもあり、とくに交渉が必要なく退職の意志だけを伝えて欲しいという方には割高に感じるかもしれません。
企業に出向いて相談・打ち合わせ等がなく、退職手続きもすべてスマートフォンで完結するため、なかなか時間が取れない忙しい方には大変便利です。
初めて退職代行サービスを利用する方や、交渉の際も費用を抑えたい方におすすめのサービスです。
| 会社名 | 東京労働経済組合 |
| 問い合わせ方法 | 電話、LINE |
| 正社員の料金 | 29,800円 |
| パート・アルバイトの料金 | 29,800円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
Re:start(リスタート)の料金と特徴
Re:startのおすすめポイントをご紹介していきましょう。
- 最短30分で職場に退職電話をしてくれる
- 業界最安水準で変わらないサービス内容
- 全額返金保証付き
2015年に設立されたRe:startは、価格の安さとスピード感に定評があります。
現在、職種に関係なく22,000円で退職代行サービスを請け負うキャンペーン中なので、気になる方はチェックしてみましょう。
民間企業であるため、弁護士が在籍・監修しているわけではなく、会社との交渉はできないので注意が必要です。
相談から最短30分で職場に退職届を提出できるスピード感もメリットの1つです。
会社との交渉が必要なく、とにかく早く退職したい場合に最適な企業となっています。
| 会社名 | 株式会社another choice |
| 問い合わせ方法 | 電話、メール、LINE |
| 正社員の料金 | 22,000円 |
| パート・アルバイトの料金 | 22,000円 |
| 追加料金 | なし |
| 最短対応 | 即日 |
退職代行の失敗とは|失敗した場合に予想される5つのリスク

次に、退職代行業者に依頼した際の失敗例をご紹介していきましょう。
そもそも退職は不可能?
退職代行業者は、労働組合や弁護士、民間企業に依頼できます。現時点では、「退職に至らない」といったトラブルはほとんど報告がありません。
高確率で、退職代行業者からの連絡を受けた企業は、業者の指示に沿って退職の対応をするようです。
もしかすると、今後、退職代行業者からの依頼である場合には退職を認めないという姿勢を強める企業も出てくる可能性はありますが、限りなくゼロに近いでしょう。
また、労働者はいつでも自由に退職できる権利があるので、会社側が退職を認めないとしても、法的には全く意味がないのです。ですので、これについてはあまり気にする必要はないでしょう。
会社に損害賠償を請求されるのか?
労働者の中には、退職をしたことで、会社から何らかの責任を問われ、損害賠償を請求されるのではと心配する人も少なくはありません。
退職代行サービスを使って退職したら、会社から訴えられたりしませんか?
中小企業で退職したい日の3ヶ月前には、退職する事を伝えて、3ヶ月間引き継ぎをしないといけないそうです。
私の仕事は、私自身しかわからないことが多く、引き続きをしずに辞めて会社に損害が出た場合は、私が訴えられて賠償金を請求されますか?
退職代行サービスを利用したい理由がいくつか、あるのですが、特定されると怖いので詳しくは書けません。
引用元:Yahoo!知恵袋
退職した従業員に対し、会社に大きな損害を与えるようなことがない限り、退職者が損害賠償を請求されることは考えられません。
(たとえ1人の社員が退職したとしても、すぐに大きな損害が発生することは考えにくいと言えるでしょう)。
ただし、これは絶対ではありません。
過去のケースでは、入社後1週間以内に退職し、退職の効力が発生するまで出勤しなかった従業員に対し、会社側が従業員に損害賠償を認め、70万円の支払いを命じた一例があります(ケイズインターナショナル事件:東京地裁平成4年9月30日判決)。
どんな退職の仕方であっても、会社が労働者の責任を一切問えないわけではないということは覚えておきましょう。
ですが、退職したその直後に会社に多大な損害が発生するということは通常ありませんので、過度にそのことを気にする必要はありません。
【関連記事】退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?
懲戒解雇をされる可能性は?
退職代行サービスを利用したことによる懲戒解雇は、法的な効力を持ちません。
懲戒解雇というのは、会社の秩序を著しく乱した労働者に対して与える罰則であり、日本では労使間で認められている最も重い罰則です。
日本の法は、労働者の地位を手厚く保護しており、企業は労働者を簡単に解雇することはできない風潮があります。
罰則としての解雇は、直ちに労働者の雇用を終了させるだけでなく、再就職にも影響を及ぼす可能性があり、労働者は大きな影響を受けることになります。
したがって、懲戒解雇が法的に有効とされるのは、会社のお金を横領するなどの実害が出るほど「重大な問題(被害)」があった場合だけです。
退職までにパワハラやいじめを受ける?
6年間勤めた不動産関係の会社を、ステップアップのために退職しようと、半年前、退職の意向を社長に伝えましたが、良いように丸め込まれてしまって、退職を受け入れてくれなかったそうです。
退職の意志が固かったこの男性は、後日、再び退職させてほしいと社長に伝えたところ、社長の態度が急変し、男性を激しく罵倒する言葉がSNSに届くようになったそうです。
そこで男性は、意を決して退職届を直接手渡しましたが、それでもまだ受理してもらえず、その場にあったペットボトルを思いっきり投げつけられ、「ふざけたこと言ってんじゃねえよ」と激しい剣幕で怒鳴られたそうです。男性は、自力での退職は厳しいと判断し、やむなく退職代行サービスを利用しました。
引用元:退職代行サービスが流行るワケ。罵倒して辞めさせない企業の驚愕実態 | bizSPA!フレッシュ
退職の効力が発生するのは、退職届を出してから2週間後です。
上記の例は極端なように見えますが、こういった行動が見られる企業は一定数存在しているでしょう。
退職時に有給休暇が残っている場合、通常最終出社日以降が有給休暇の期間とみなされるため、有効に活用するようにしましょう。
有給休暇を使い切ることが難しいケースであれば、退職時点までの出勤状況について会社に掛け合ってみてください。
退職後、必要書類を送ってもらえない?
退職時に、離職票などの今後必要になる書類を送付してもらったり、会社に置いてある私物を返却してもらったりする必要があります。特に離職票は、雇用保険の手続きをする際、必ず必要になる重要な書類です。
しかし、会社側が書類を送ってこなかったり、私物が返却されなかったりすると、無事に退職が成立しても素直に喜べないですよね。
2月末で精神的な病気を理由に退職しました。
3月に入ってもなかなか離職票などの必要な書類を送ってもらえず、何度も催促し、今日やっと雇用保険被保険者離職証明書が送られてきたのですが…
もし失業手当を貰う手続きをするとしたら、この書類と印鑑などの必要なものをハローワークに持参し手続きをすればいいのでしょうか?
退職日から一ヶ月も経ってしまっているので、失業手当を貰うことはできないのでしょうか?
引用元:Yahoo!知恵袋
退職代行サービス利用の有無に関わらず、退職後にこのようなケースが発生してしまうことがあります。まず、速やかにハローワークや労働局に相談するようにしましょう。
一番の失敗は非弁業者に依頼すること
退職代行の依頼時に、最も問題となる失敗のパターンは、「代行をしない業者」についてです。
現在、業者が退職代行をすることは、弁護士法で禁止と指定されている『非代理業務』に該当する可能性が高いとの声が相次いでいます。
非代理業務とは、弁護士でない者が交渉などの法律事務を業務として行うことです。弁護士資格を保有していない退職代行者が、利用者の依頼を受け、退職に関する「交渉」を行った場合は、弁護士法違反となります。
最近、退職代行業者が注目されている中、退職代行事業に参入する企業も少なくありません。依頼した退職代行業者が弁護士資格を持っていなかった場合は、トラブルに発展する可能性があります。
例えば依頼した非代理店が警察に摘発された場合、警察から連絡が来て事情聴取を受ける場合もあり、退職代行サービスを利用しただけなのに・・・と嫌な気持ちになってしまいます。
退職代行サービスを運営している業者を利用する際は、退職の時に交渉してほしいかどうかで依頼先の業者を選択する必要があるのです。
退職代行を失敗させないための3つの方法

では、退職代行の利用時に失敗しない方法とは、どのようなものでしょうか?
『最低限』顧問弁護士のいる業者に依頼する」
退職代行サービスの業者には、弁護士の資格を持っていない「退職代行業者」と、退職代行サービスを扱う「弁護士」の2種類があります。このうち、無資格の退職代行業者を利用する場合は、「弁護士ではない」事務所を選ぶ必要があります。
弁護士ではない業者の見分け方としては、「顧問弁護士」がいるかどうかを確認することです。
顧問弁護士がいる業者は、コンプライアンスに適合している可能性が高いですが、絶対に安全というわけではありません。顧問弁護士がいても、不適合かどうかをきちんと検討しているとは限らないのです。
また、契約者が顧問弁護士のアドバイスに従わない可能性もあります。顧問弁護士をつけることは、あくまで「最低条件」であり、十分条件ではないことに注意しましょう。
相談時にどこまで対応してくれるか確認する
優秀な退職代行業者は、弁護士法の観点から、自社でできることの限界を説明してくれます。しかし、弁護士資格を保有していない退職代行者は、「そのまま退職の意思を会社に伝える」ことしかできません。それ以上の交渉は法律でできないと定められているからです。
有給の問題、退職時期の調整、残業代の請求について全て解決することが可能だと掲げている企業は、違法業者である可能性が非常に高いでしょう。
最も安心なのは、退職代行を請け負う弁護士
無資格の退職代行業者は、どうしても「代理権がない」というリスクを抱えてしまいます。退職代行業者が実際にどのように会社と話をしているのか、依頼者は見ることができないため、絶対に大丈夫とは言い切れません。
不払いのリスクを最小限にするためにも、退職代行を依頼するのは「弁護士」にしましょう。
弁護士自身が退職代行者であれば、不払いは起こりません。有給の使用や購入、退職金の金額やタイミング、未払い残業代まで合法的に請求することができます。
まとめ
退職したいのに、弁護士資格を持っていない退職代行業者を選んでしまうと、失敗するリスクが一気に高まります。
より確実で有利な退職をしたいのであれば、弁護士の資格を持っている人に依頼すべきでしょう。
もしあなたが退職代行業者を利用する場合は、まず労働問題を得意とする弁護士を探し、退職の相談をするようにしてみてくださいね。




コメント